理論在庫と実在庫のズレが生じる原因
商品の在庫を管理する表、専用のシステムに記録されている在庫を「理論在庫」と言い、実際に倉庫にある在庫を「実在庫」と言います。
両者が常に一致しているのが理想ですが、業務の都合上、ズレが生じることがほとんどです。
そのズレを放っておくと、在庫不足で出荷が遅れてしまう、実在庫はあるがシステムでは在庫なしになっているなど、企業にとってマイナスな事象が起きてしまいます。「売れるはずの商品が売れなかった」では、済まされない問題です。
それでは、なぜ理論在庫と実在庫にズレが発生してしまうのでしょうか?
よくあるケースとしては、「仕入れた商品の数と管理表に入力した数が間違えていた」という人為的ミス。または「入力が遅れてしまった」「廃棄した数が管理表に反映されていない」「商品が別の場所に移動されていた」などの原因もあります。
在庫のズレは企業のイメージダウンに影響することも考えられるため、在庫管理を徹底して、在庫処分の手間も軽減しましょう。
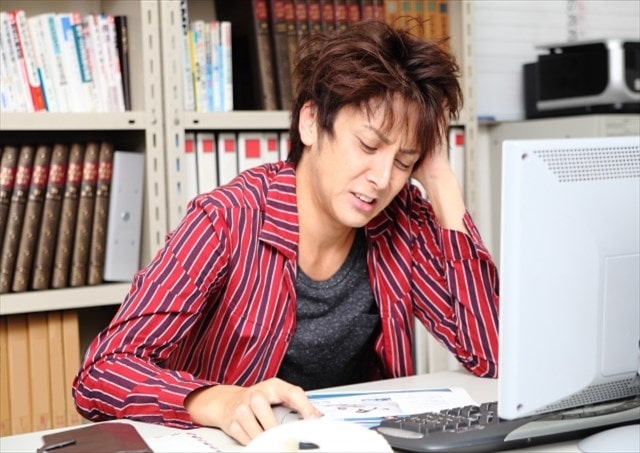
ファッション製品の過剰在庫が発生する3つの理由とは
ファッション業界において、そもそも何故、過剰在庫が発生するのかについて、考えてみましょう。
過剰在庫の意味を辞書から引用すると「需要以上に生産したため売れ残り、店舗や倉庫などに蓄積している商品を意味する表現。」とあります。
それではなぜ、それほどまでに店舗や倉庫に商品が蓄積されてしまうのでしょう?
1つ目に、繊維・ファッション業界特有の複雑な業界構造があげられます。
2つ目には、「移り変わりやすいファッショントレンド」が大きな原因として考えられます。
そして3つ目には、「高すぎる品質基準」があると考えられます。
以下に具体的に考えていきます。
理由1.繊維・ファッション業界特有の複雑な業界構造
繊維・ファッション業界は”川上”から”川下”に至るまで、永くに渡って分業化が行われてきた業界です。原材料をつくる”川上”から辿っていくと、綿やウール等の原料を調達する原料メーカー、それを糸にする紡績メーカー、さらにそれを織物や編み物にする機屋、ニッターなどなど。
これらの「”川上”で出来上がった素材・生地」を、製品化していくのが”川中”の役目です。”川中”は、裁断・縫製する縫製メーカー、それらを一貫して調整する繊維商社、商社から自社の企画にあった生地を仕入れ製品化して販売するアパレルメーカー等が存在します。
そして、最終的に一般消費者に向けて販売する百貨店、量販店、ファッションビル等のデベロッパーが”川下”と呼ばれ、更にこれらサプライチェーン間にも在庫を備蓄する問屋が存在します。
これほどまでに多くのサプライヤーが存在する中で、それぞれのサプライチェーン間には当然ながら製造ロット・仕入れロットが存在し、原料・糸を仕入れるなら何キロから、生地を仕入れるなら何mから、製品を仕入れるなら何枚から、という具合に、必ずしも自社・得意先が必要とする数量のみを仕入れられるわけではありません。
よって、この段階で既に「消費者が求める適正な数量のみ」を製造することは、非常に困難であると言えます。
更には、小売店では「消費者の求める商品」を常に在庫しておかないと、売れるシーズンに売れるものを販売できない(機会損失)を起こしてしまう為、小売店での欠品を避けるために、小売店に納めるサプライヤーは見込みで少し多めに生産しておきます。
もちろん毎回見込み通りに売れるわけではないため、需要を読み違った商品は「過剰在庫」として残ってしまう、というわけです。
理由2.移り変わりやすいファッショントレンド
数年間続くビッグトレンドもありますが、他の産業と比較しても圧倒的に消費トレンドのスピードが速いファッション市場では、顧客のニーズに沿った商品を提供するために毎月一回展示会を開催し、毎年新商品を数百型も発表し続けるアパレルOEM/ODMメーカーも少なくありません。
展示会で受注した商品を最短納期で得意先であるバイヤーの店頭に陳列する為に、前シーズンの売れ筋や欧米諸国のトレンドから予測し見込みで少し多めに生産しておくのです。
もちろん常に予測通りに売れるわけではないため、需要を読み違い、見込みで生産した商品は「過剰在庫」として残ってしまうというわけです。
理由3.アパレルの高すぎる品質基準
“川下”のデベロッパーから”川上”のメーカーや商社に至るまで、消費者からのクレームを回避するために業界全体として一定の品質基準を設けています。その品質基準に満たない商品は「不良品(B品)」として取り扱われ、その商品の一部はアウトレットモール等で販売されることもありますが、多くは世の中に流通することはありません。
それでは、どのような基準で不良品と見なされているかというと、基本的には「納品先の基準」に沿う形になりますが、納品先ではない商品の品質を検査する第三者機関がいくつか存在し、そこで検査した検査結果が納品先の基準(百貨店基準や量販店基準等)に満たない場合に、大量に生産した後であったとしても「納品すら許されない」自体が生じます。
それらの不良品(?)は、得意先との関係上どうしても廃棄をせざるを得ない場合もあり、その中には例えば”色ぶれ”と言う「納品先が指定した色と多少の誤差があるだけのもの」や、”とびこみ”という「1mmほどの綿くずのようなものが生地に織り込まれてしまっているだけのもの」など、ユーザーである消費者が気にするかどうかですら不明なものも、多く含まれます。
事実、スマセルの出品者様から寄せられた声として、得意先から「不良品」として返品されてきた商品の不良箇所を確認した際にも、「どこが不良なの?」と目を疑うケースもよくあるそうです。

在庫処分に変化が起き始めているアパレル業界。
繊維ファッション業界の在庫は積み上がっていきます。
ですが必ずしも悲観的な話ばかりではありません。少しずつ、業界全体の問題意識は変わりつつあります。
たとえば、そもそも作りすぎを無くすSCM(サプライチェーンマネジメント)を利用した取り組みであったり、作りすぎたものをうまく活用していく取り組みも広がって来てます。
特徴的な事例としては、フランスのファッションブランド「ヴェトモン(VETEMENTS)」は、今年、店頭のショーウィンドーを古着の山で埋めるインスタレーションを実施しています。
「ヴェトモン(VETEMENTS)」がこのインスタレーションを作った目的は、消費者に「大量生産・大量消費問題への関心を高めてもらうこと」と、ブランドに「市場を異常なほど飽和させていることや、地球に悪影響を与えることに対して罪悪感を抱いてもらうこと」だといいます。
他にもヴェトモン(VETEMENTS)は、ファーストコレクションで『リーバイス(LEVI’S)』のビンテーンジジーンズをリメイクしたように、古く使用されなくなったものに第2の命と新しい用途を与えてきました。
こうした動きは海外だけでなく、日本国内でも、大手セレクトショップのアーバンリサーチが、在庫となっている衣服をアップサイクルして新たに付加価値のある製品として販売するサステナブル・プロダクト・ブランド「commpost(コンポスト)」を立ち上げたりしています。
在庫〜廃棄の問題が深刻化する繊維・ファッション業界において、今後このような取り組みが更に拡大し、広がっていくことを期待する一方で、スマセルとしては、在庫処分の新たな選択肢として再流通の場を提供・拡大することに全力を注ぐ次第です。

お得に買って、地球を守る。
Sustainable Outlet Mall




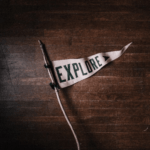


Comment